「宮殿泥棒」 イーサン・ケイニン ― 2007年09月07日 23時08分52秒
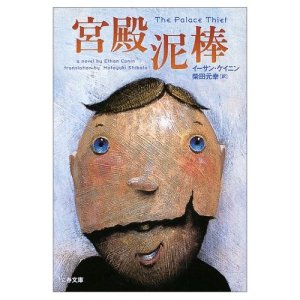
「宮殿泥棒」 イーサン・ケイニン
THE PALACE THIEF
by Ethan Canin
(文藝春秋)
中年期以降の男性を主人公としたヒューマンドラマ的な物語の短編集。収録作は「会計士」「パートルシャーグとセレレム」「傷心の街」「宮殿泥棒」の4編。
「会計士」 40代中年男性の優等生会計士と成功した遊び人タイプの幼なじみの話。
「パートルシャーグとセレレム」 勇気と愛(ハンガリー語) 天才の兄とそこそこ優等生の弟の話。
「傷心の街」 50代で妻に去られた良き夫、良き父の男と息子の話。
「宮殿泥棒」 生真面目に生きてきた老教師と問題児の話。
興味を持ったのは「宮殿泥棒」が、映画「卒業の朝」の原作だと教えてもらったから。
「卒業の朝」はケヴィン・クラインが老教師を演じたなかなかヒューマンドラマとしても青春ドラマとしても見応えのある1本だった。
老教師が理想とする教育方針を純粋に貫いたために出世を阻まれ、さらに昔の苦い過去を突きつけられる、ちょっと辛い話だ。
引退した彼の元に今や上院議員に立候補しようという時の人たる昔の教え子から再会を求められる。まだ血気盛んな教師であった頃、超問題児が転校してきたが彼がその人。彼の処遇によってクラインは教師として痛い体験をしたのだが、彼が今になってその時の再現を申し出てきた。
映画の面白さを損ないたくないので詳しくは述べないが、教師の理想として、正しい人間として、微妙な心のひだを抉るようなこの物語は、教師という職業に関係なく、普通の生活を送る人ならば誰でも苦い気分を味わう話ではないかと思う。
問題児の少年期を演じたエミール・ハーシュがかなり憎たらしい。(笑)
少年たちの中で中心となる問題児の影に葬られてしまったかのような少年が一人いる。この彼の存在が、原作よりも映画のほうで非常に印象的な使われ方をしており、クライン演じる老教師の大きな心の救いになっているように感じられた。
その少年の成長後を演じたスティーヴン・カルプが地味ながら、地味だからこそ意味があるこの作品の独特の味を象徴付けている。
今までにいろんな小説を読んできたが、中年から老年にかけた男性が主人公で、サスペンスでもSFでもない、真正面から彼らの人生、心情に訴えた作品というのは初めてだった。
「卒業の朝」は学園が舞台にあることと大きな事件が舞台にあるので映画化されたのも納得だが、他の短編はなかなか難しいだろうなと思うほど地味な作品だ。
優等生としてそつなく人生を送ってきた男たち。
おちこぼれであってもひとつのアイデア、ひとつの勝負で成功する男。アメリカンドリームの実現を見せるそんな男の話の方が話題になるし面白いに決まっている。
ところがこれらのケイニンの作品の主人公たちは、優等生として面白味もなく話題になることもなく地味に生きてきた男たちだ。しかし、彼らをいじけて閉じこもったり、犯罪に走らせるでもなく、彼らなりの答えを見つけ、自分の人生を再確認する物語にしているのが珍しく面白い。
この世の中、アメリカンドリームを体現している男たちばかりが生き残っているわけではない。むしろ、この日本においては、こういう地味に頑張ってきた優等生の男たちによってそのほとんどが作られてきたと言っても過言ではないのではないだろか。
面白くなくても、彼らには彼らの信条があり、生きる意味があり、振り返って確認するだけの意味のある人生なのだ。
途中でどんなに惨めなことになっても、それを受け止めて前を向いて生きていく力だって持ち合わせているのだ。
華やかな人生を生きている奴にだけ、恩恵があるだなんて思うなよ!
どんな普通の人にもちょっと、勇気と余裕ををもらえる物語の数々。痛みを感じながらも、なんだか頷けてほっとしてしまう話ばかりだった。
THE PALACE THIEF
by Ethan Canin
(文藝春秋)
中年期以降の男性を主人公としたヒューマンドラマ的な物語の短編集。収録作は「会計士」「パートルシャーグとセレレム」「傷心の街」「宮殿泥棒」の4編。
「会計士」 40代中年男性の優等生会計士と成功した遊び人タイプの幼なじみの話。
「パートルシャーグとセレレム」 勇気と愛(ハンガリー語) 天才の兄とそこそこ優等生の弟の話。
「傷心の街」 50代で妻に去られた良き夫、良き父の男と息子の話。
「宮殿泥棒」 生真面目に生きてきた老教師と問題児の話。
興味を持ったのは「宮殿泥棒」が、映画「卒業の朝」の原作だと教えてもらったから。
「卒業の朝」はケヴィン・クラインが老教師を演じたなかなかヒューマンドラマとしても青春ドラマとしても見応えのある1本だった。
老教師が理想とする教育方針を純粋に貫いたために出世を阻まれ、さらに昔の苦い過去を突きつけられる、ちょっと辛い話だ。
引退した彼の元に今や上院議員に立候補しようという時の人たる昔の教え子から再会を求められる。まだ血気盛んな教師であった頃、超問題児が転校してきたが彼がその人。彼の処遇によってクラインは教師として痛い体験をしたのだが、彼が今になってその時の再現を申し出てきた。
映画の面白さを損ないたくないので詳しくは述べないが、教師の理想として、正しい人間として、微妙な心のひだを抉るようなこの物語は、教師という職業に関係なく、普通の生活を送る人ならば誰でも苦い気分を味わう話ではないかと思う。
問題児の少年期を演じたエミール・ハーシュがかなり憎たらしい。(笑)
少年たちの中で中心となる問題児の影に葬られてしまったかのような少年が一人いる。この彼の存在が、原作よりも映画のほうで非常に印象的な使われ方をしており、クライン演じる老教師の大きな心の救いになっているように感じられた。
その少年の成長後を演じたスティーヴン・カルプが地味ながら、地味だからこそ意味があるこの作品の独特の味を象徴付けている。
今までにいろんな小説を読んできたが、中年から老年にかけた男性が主人公で、サスペンスでもSFでもない、真正面から彼らの人生、心情に訴えた作品というのは初めてだった。
「卒業の朝」は学園が舞台にあることと大きな事件が舞台にあるので映画化されたのも納得だが、他の短編はなかなか難しいだろうなと思うほど地味な作品だ。
優等生としてそつなく人生を送ってきた男たち。
おちこぼれであってもひとつのアイデア、ひとつの勝負で成功する男。アメリカンドリームの実現を見せるそんな男の話の方が話題になるし面白いに決まっている。
ところがこれらのケイニンの作品の主人公たちは、優等生として面白味もなく話題になることもなく地味に生きてきた男たちだ。しかし、彼らをいじけて閉じこもったり、犯罪に走らせるでもなく、彼らなりの答えを見つけ、自分の人生を再確認する物語にしているのが珍しく面白い。
この世の中、アメリカンドリームを体現している男たちばかりが生き残っているわけではない。むしろ、この日本においては、こういう地味に頑張ってきた優等生の男たちによってそのほとんどが作られてきたと言っても過言ではないのではないだろか。
面白くなくても、彼らには彼らの信条があり、生きる意味があり、振り返って確認するだけの意味のある人生なのだ。
途中でどんなに惨めなことになっても、それを受け止めて前を向いて生きていく力だって持ち合わせているのだ。
華やかな人生を生きている奴にだけ、恩恵があるだなんて思うなよ!
どんな普通の人にもちょっと、勇気と余裕ををもらえる物語の数々。痛みを感じながらも、なんだか頷けてほっとしてしまう話ばかりだった。


最近のコメント